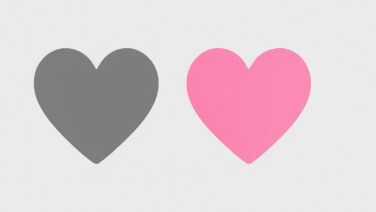 故事成語
故事成語 友情と恋愛のグレーゾーン!灰色ハートの真の意味とは
灰色ハート(グレーハート)の本当の意味とは?友情と恋愛の間にある微妙な気持ちを表すグレーのニュアンスを詳しく解説。色別ハートの使い方や誤解を防ぐポイントも紹介します。
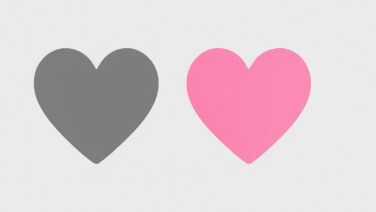 故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語 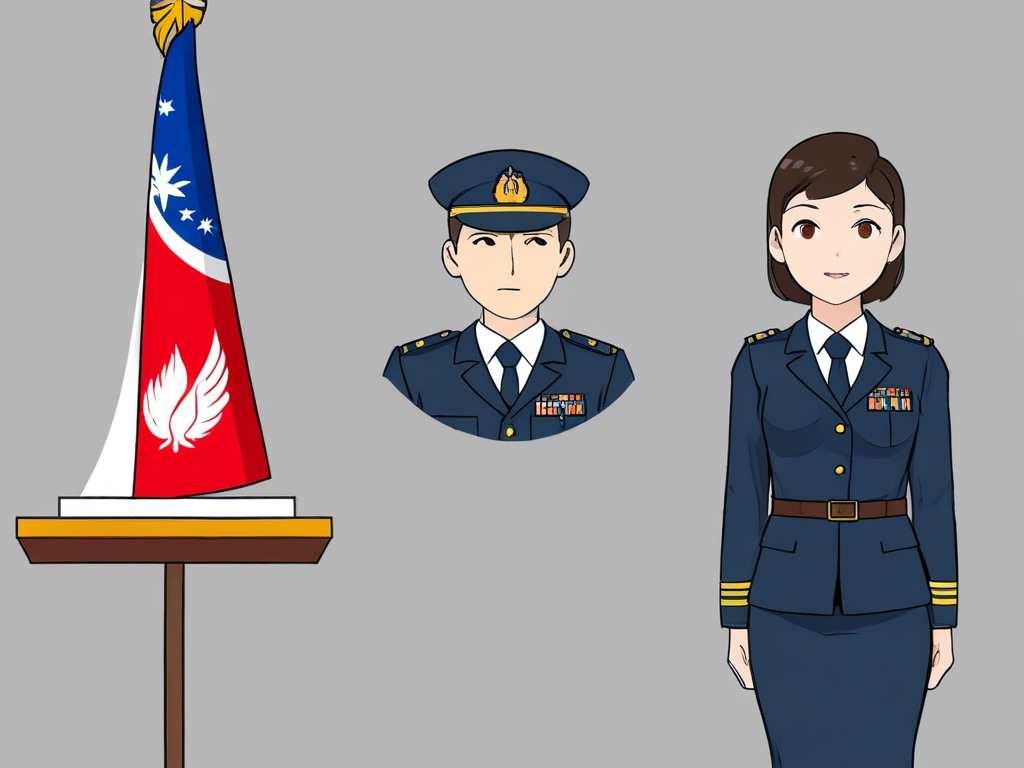 故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語