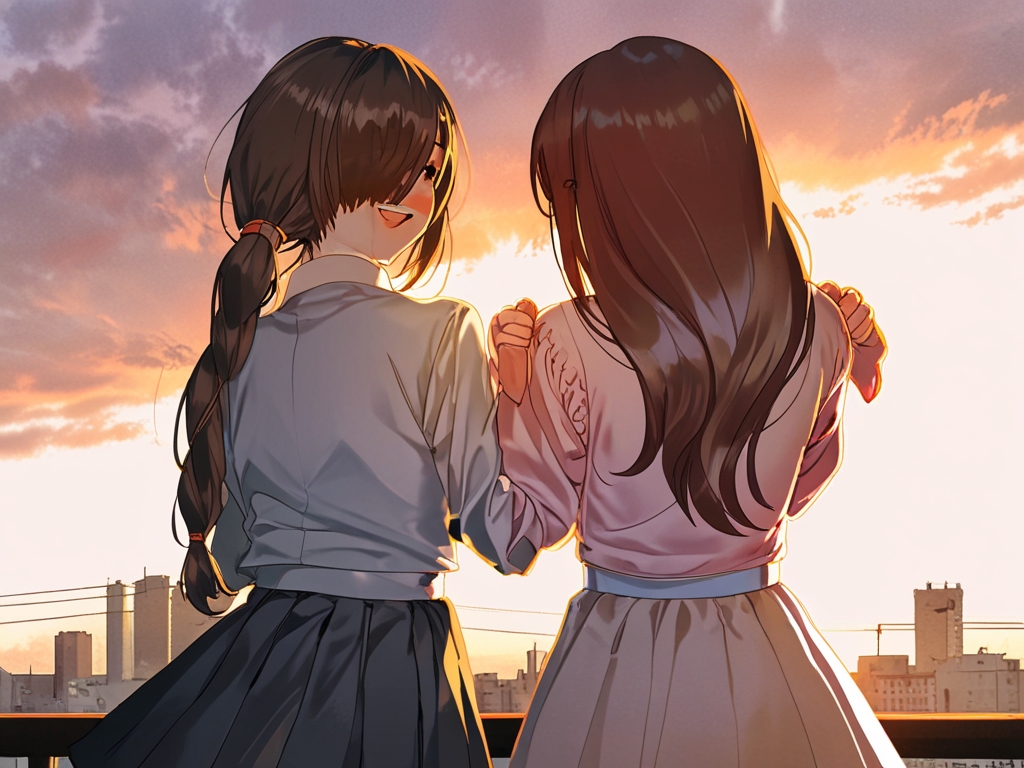 故事成語
故事成語 管鮑の交わりとは?どういった意味なの?
管鮑の交わりとは、どんな状況でも壊れることのない深い友情を指します。この言葉は、管仲と鮑叔という二人の友人のエピソードから来ています。二人の名字を取って「管鮑の交わり」と呼ばれるようになりました。最初、管仲と鮑叔は異なる国に仕えており、時に...
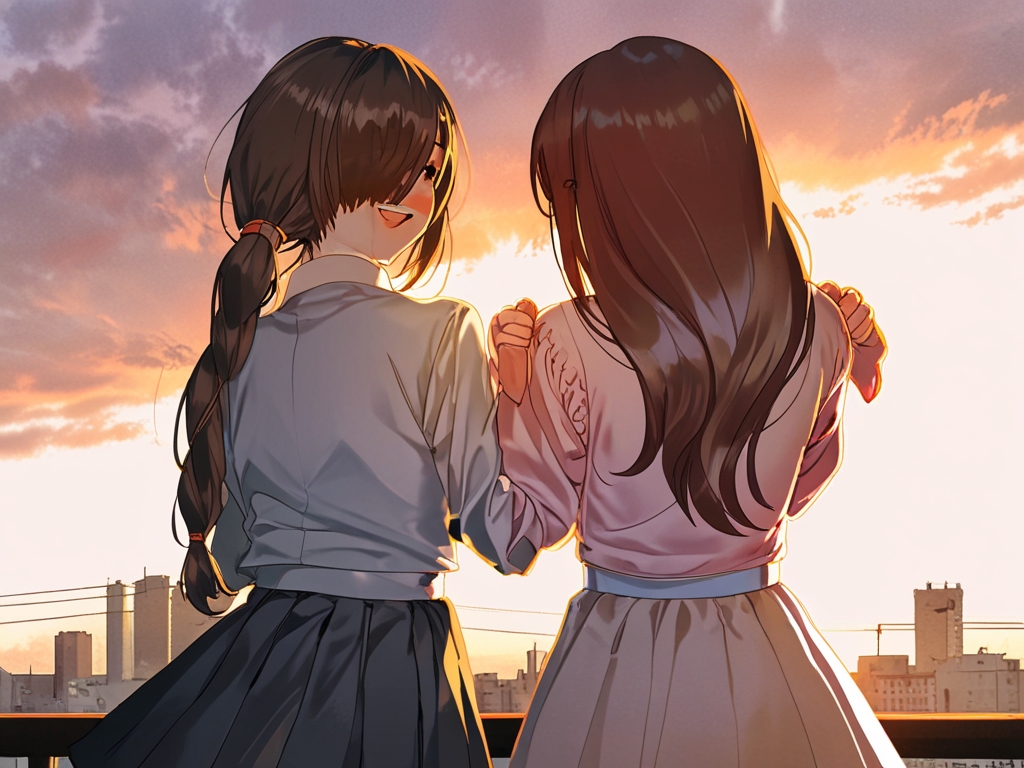 故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語 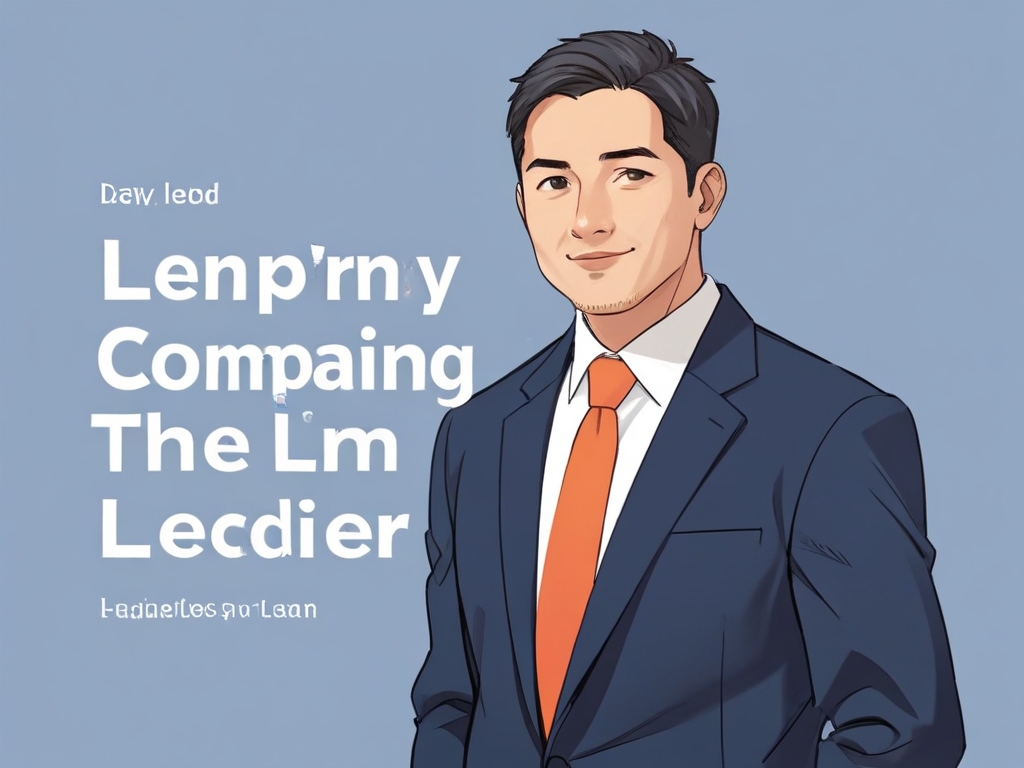 故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語