 故事成語
故事成語 漁夫の利の由来とは?
漁夫の利とは、争っている当事者たちの間で第三者が利益を得ることを指します。この言葉は、両者が争っている間に第三者がうまく利益を得るさまを示すことわざです。「漁夫」は本来漁師を指しており、その起源には独特の意味があります。「漁夫の利」は、両者...
 故事成語
故事成語 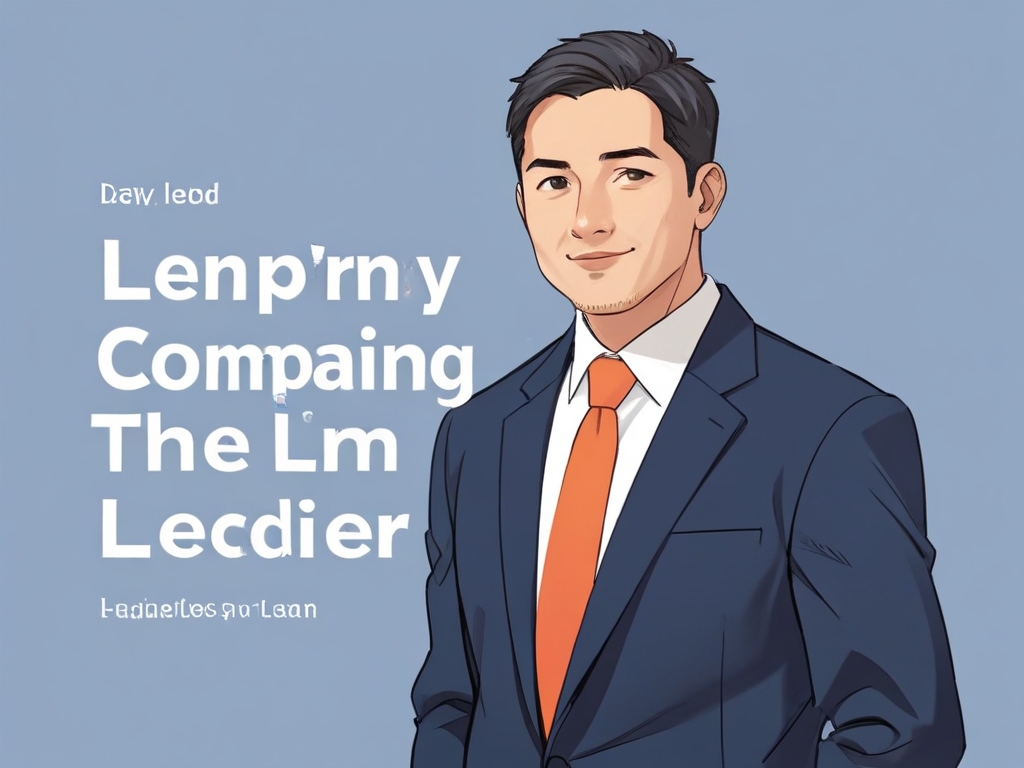 故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  郷土料理
郷土料理  郷土料理
郷土料理 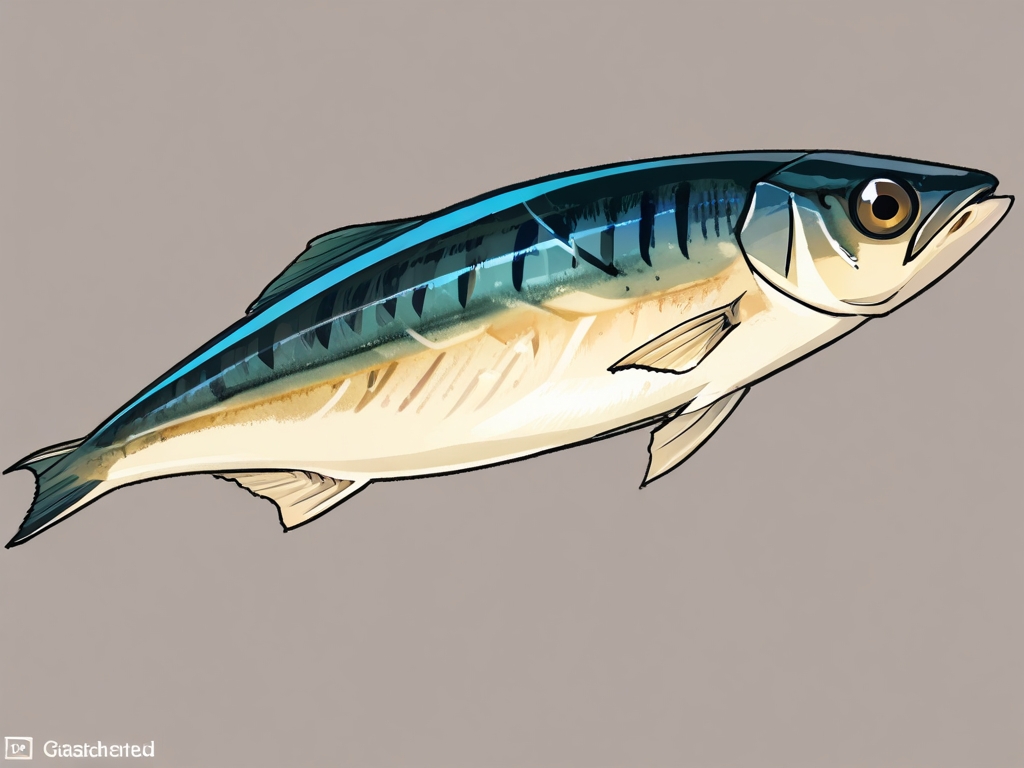 郷土料理
郷土料理  郷土料理
郷土料理  郷土料理
郷土料理  似た言葉の違い
似た言葉の違い 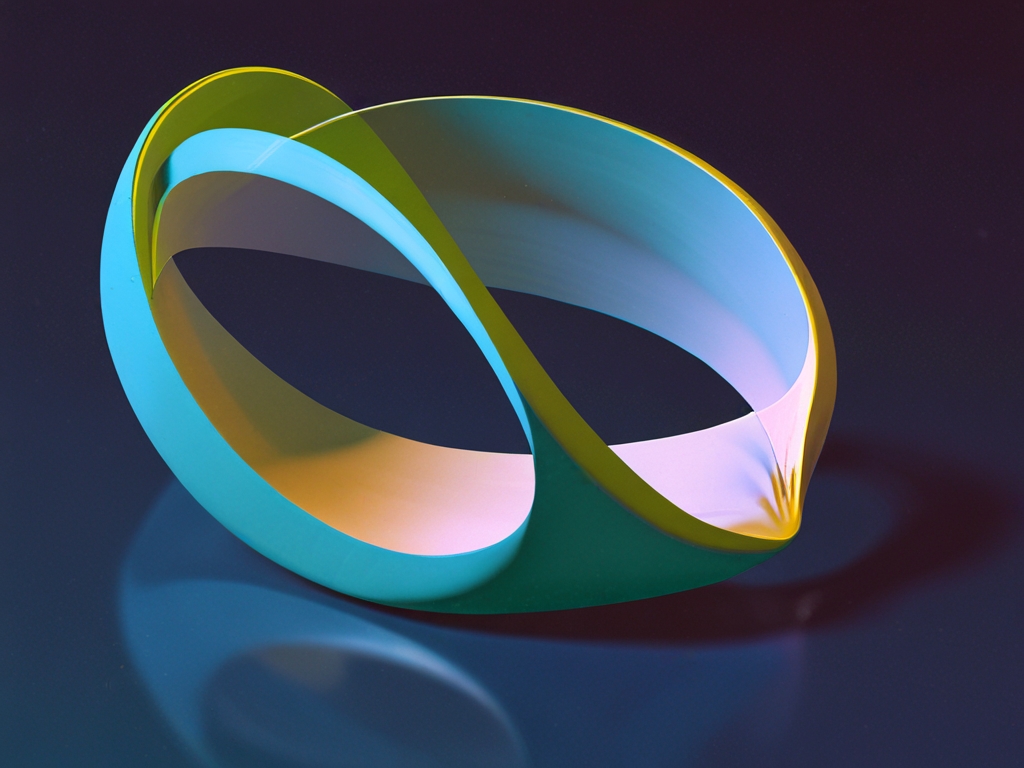 似た言葉の違い
似た言葉の違い  似た言葉の違い
似た言葉の違い  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  故事成語
故事成語  郷土料理
郷土料理  郷土料理
郷土料理  郷土料理
郷土料理  行事の由来
行事の由来